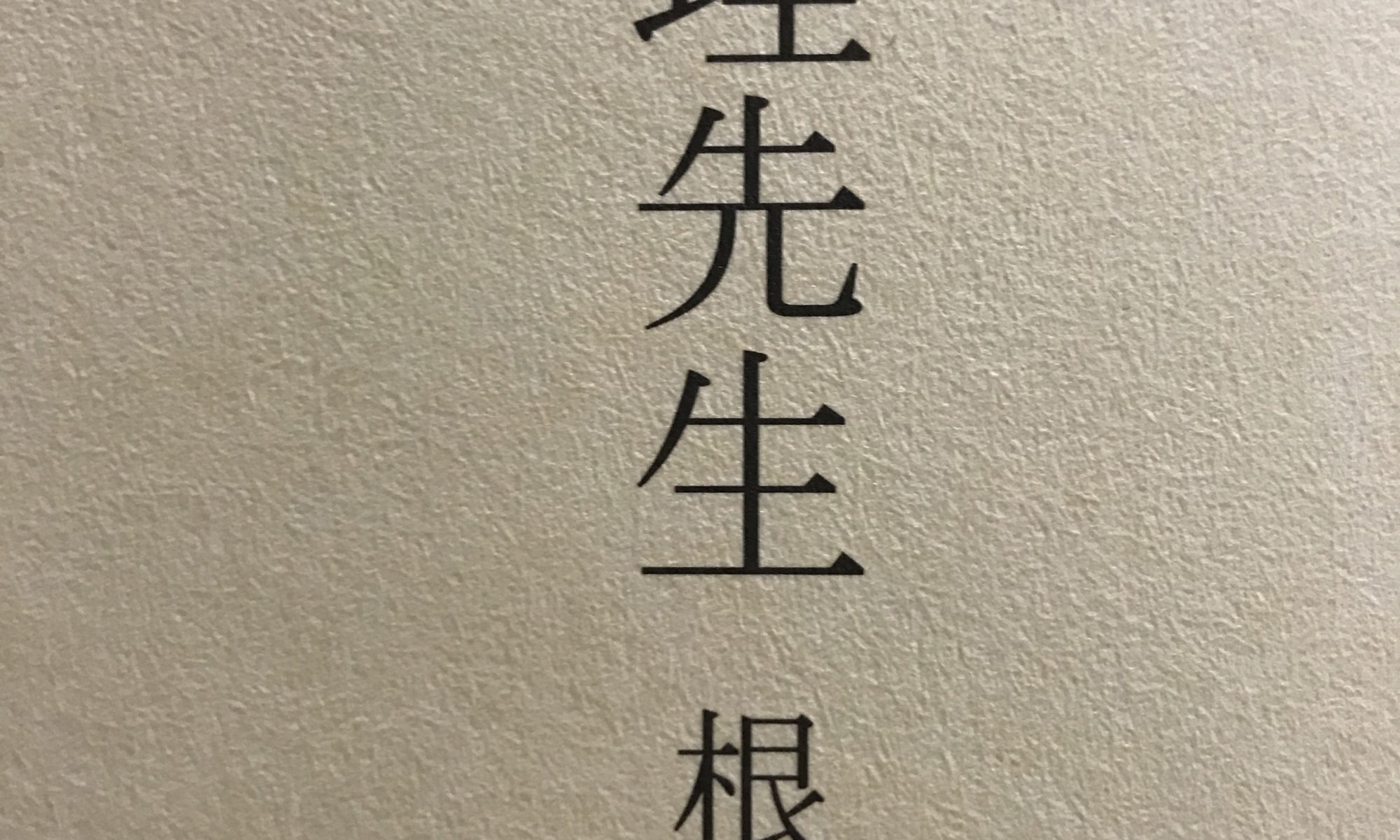僕がこの本を実際に読んだのは、2020年8月。正直、本作について語るには、その当時でさえ遅きに失していた感はある。すでにYou Tubeで中田敦彦氏がエクストリームに解説していたし、感想や書評は、少し検索すれば、いたるところで見かける。なので、今回はあらすじには触れない。未読の方は、他の方のレビュー等も参考にしつつ、興味を持っていただけたら是非手にとってみてほしい。
本書の発行日は2019年6月20日。僕の手元にあるのは、21刷目。重版に重版を重ね、売れ続けている本である。
本書で「ぼく」と「母ちゃん」が遭遇するものは、ざっくりといえば「差別」と「分断」だ。現代において、それらは一見なくなったように見えて実は可視化されにくくなっただけだったり、解決どころかよりややこしくなっていたり、ジェンダー(LGBTQの問題を含む)の問題のように、新しい視点が必要だったりする。
本書は、英国の「荒れている地域」のお話だ。こういった舞台ですぐにパッと浮かぶのは、人種差別やヒエラルキーによる差別といったところか。だが人種差別ひとつとっても、白人→有色人種という単純なものばかりではない。移民同士の中でさえ、いや、むしろ「〇〇とそれ以外」の、「それ以外」の中こそ、分断や差別はより苛烈になることもある。居住地域による教育や経済の格差、差別感情(明確な意識ではなくても「感情」を持ってしまう人は多いのでは)などは、現代日本でも身近に感じるものではないだろうか。「正しさ」で殴り合う人々や、特定の国にルーツをもつ人たちへの悪罵なども、SNS界隈ではあるあるすぎる光景だ。これは、遠い国だけで起こっている話ではない。
それらの問題が渦巻く世界のなかで、「ぼく」は、一つ一つの問題にぶち当たりながら、それを解決(あくまでも個人的なレベルで)していく。その過程が実に男前なのだ。本書をドキュメンタリーとして読むのであれば、差別や格差、英国の穴だらけの福祉(実際読んでみて「うわぁ……」と感じた)などのファクトの部分を読んでいく読み方となるが、僕は「ぼく」と、彼を取り巻く子ども達の、成長と青春のストーリーとしても、是非読んでほしいと思う。読み終えたあと、「ぼく」の目線と「母ちゃん」の目線で、自分の住む世界をもう一度見直す。本書の言葉でいうならば、「誰かの靴を履いてみること」で、きっと様々な気付きがあるはずだ。